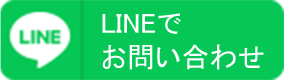歴史と特徴
華道は「生け花」という呼び方で知られる日本の伝統文化です。水盤という底の浅い平らな器に四季折々の花や草木を生けて作品を作り上げます。
古来、人類は死者を弔うために花を添えるということを行っており、日本人も花を仏さまに供え、松や榊を神様に供え、今でも花と関わって生活しています。切り花を愛でるようになり、生け花として現在のような形になったのは室町時代のころと言われています。
生け花には様々な流派があり、その数は400くらいあると言われていますが、どの流派も基本の形は同じで、2本の枝と1本の花をもとに構成されています。
生け花は非常に合理的にできています。自然の美を表現するうえで無駄なものはそぎ落としていく、というのが基本的な考え方です。よく、西洋のフラワーアレンジメントは「足し算」、生け花は「引き算」にたとえられますが、枝や花を生けるときにも無駄な葉や小枝は切り落としていきます。
どこが必要でどこが必要でないのか見極め、目の前にある花と向き合って決めていきます。そうして枝と花の間に作り出される空間が心地よく美しく見えるのが生け花の特徴です。
生け花に使う道具
始めに必要なものは、花ばさみ、剣山、花器(水盤) です。
花ばさみ
花ばさみは最初から高価なものを買う必要はありませんが、枝を切り落としたり、花を切るのに適している生け花用のものが良いです。

剣山
剣山は花材を固定するための道具で、円形または四角形の金属製の台に針状の突起が並び、くしのような見た目をしています。水を入れた花器の中に置いて、花を生けるのに使います。

花器(水盤)
花器はいろいろな形のものがありますが、生けるときに自然な枝の流れや曲線を活かしやすいので、最初は丸型の水盤を使います。口が広く浅い器で水もたっぷり入るので、花も長持ちします。

生け花の基本の型
基本の生け花は2本の枝と1本の花をもとに形作ります。
2本の枝は同一の花材を使います。2本の枝のうち1本は主役として生け、もう1本は準主役として生けます。主役の枝を一番長くし、準主役の枝はそれより短くします。そして脇役として生ける花は一番短くします。この3本を決まった角度をつけて剣山に刺して生けるのが基本の形です。
フラワーアレンジメントのようにたくさんの種類の花材を使わなくても枝と花の空間を活かした華やかな作品ができあがります。